みなさん、こんにちは!
今回は、日本の歴史の中でも特に面白い時代の一つである室町時代にタイムスリップして、その時代の政治の中心だった「室町幕府(むろまちばくふ)」の仕組みについて、じっくりと探っていきましょう。
室町時代ってどんな時代だったか、覚えていますか?そうです、武士たちが活躍した鎌倉時代の次に来る時代で、「足利尊氏」(あしかが たかうじ)という人が新しい政府を京都に作った時代のことですよ!この室町幕府は、鎌倉幕府とはまた違ったユニークな仕組みを持っていたんです。
さあ、一緒に室町幕府の秘密を解き明かしていきましょうね!
室町幕府って何だろう?
室町幕府というのは、鎌倉時代が終わって、日本の政治をリードするために足利尊氏が京都の室町に開いた武士の政府のことなんです。
「鎌倉幕府」が「源頼朝」(みなもとの よりとも)によって開かれたのと同じように、武士が日本の中心に立った時代なんです。
室町時代は、今からおよそ600年前から500年くらい前、だいたい1336年(北:建武3年/南:延元元年)から1573年(元亀4年/天正元年)まで続いたんです。とても長い間、日本の政治を動かしていたんですね!
なぜ「室町」幕府なの?
これは簡単ですね!「足利義満」(あしかが よしみつ)という三代目の将軍が、京都の「室町」という場所に、豪華な「花の御所(はなのごしょ)」という将軍の家を建てたから、その場所の名前を取って「室町幕府」と呼ばれるようになったんですよ。
それまでは、場所の名前が変わるたびに「京都幕府」とか「足利幕府」とか呼ばれることもあったそうです。でも、やっぱり「室町幕府」という呼び方が一番しっくりきますよね?
室町幕府のトップ、将軍ってどんな人? 👑
室町幕府のトップに立つ人は、「征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)」、略して「将軍」と呼ばれていました。この将軍が、まさに日本の最高権力者だったんです。鎌倉幕府と同じように、武士たちのリーダーとして、国全体を動かす役割を担っていました。
将軍は、日本の政治だけでなく、軍事のトップでもありました。だから、戦争が起こると、将軍が作戦を立てて、全国の武士たちに命令を出していたんです。将軍の周りには、たくさんの優秀な家臣たちがいて、将軍を支えていました。
でも、将軍といっても、常に絶対的な権力を持っていたわけではないんですよ。特に室町時代の中盤以降は、周りの有力な「守護大名」(しゅごだいみょう)たちとの関係や、将軍自身が持っている力によって、その影響力は大きく変わっていったんです。
室町幕府の主な役職を見てみよう! 🏢
室町幕府には、将軍を助けて政治を動かすために、たくさんの役職がありました。まるで、現代の政府に色々な省庁があるのと同じような感じですね!ここでは、特に重要な役職をいくつか紹介します。
- 管領(かんれい) 📋
- 管領は、将軍の次に偉い役職で、将軍を補佐して幕府の政治を総括する存在でした。室町幕府の創設に功績のあった、「細川氏」(ほそかわ)、「斯波氏」(しばし)、「畠山氏」(はたけやまし)の三家が交代で務めるのが慣例でした。
これを「三管領(さんかんれい)」と呼びます。彼らは将軍の意思を汲み取り、幕府の政策を実際に動かす重要な役割を担っていたんですよ。
- 管領は、将軍の次に偉い役職で、将軍を補佐して幕府の政治を総括する存在でした。室町幕府の創設に功績のあった、「細川氏」(ほそかわ)、「斯波氏」(しばし)、「畠山氏」(はたけやまし)の三家が交代で務めるのが慣例でした。
- 侍所(さむらいどころ) ⚔️
- 侍所は、幕府の軍事と警察の役割を担っていました。京都の治安を守ったり、将軍の命令を各地の武士に伝えたり、罪人を捕まえたりする仕事をしていました。現在の警察庁のようなイメージですね。
侍所の長官は「所司(しょし)」と呼ばれ、やはり有力な大名たちが務めました。こちらも、「赤松氏」(あかまつし)、「一色氏」(いっしきし)、「山名氏」(やまなし)、「京極氏」(きょうごくし)の四家が交代で務めることが多く、「四職(ししき)」と呼ばれました。
- 侍所は、幕府の軍事と警察の役割を担っていました。京都の治安を守ったり、将軍の命令を各地の武士に伝えたり、罪人を捕まえたりする仕事をしていました。現在の警察庁のようなイメージですね。
- 政所(まんどころ) 💰
- 政所は、幕府のお金や文書に関する仕事を担当していました。幕府の財政を管理したり、土地の所有権に関する書類を作成したり、訴訟の受付をしたりするなど、幕府の事務全般を担う機関でした。現代の財務省や法務省のような役割を兼ね備えていたと言えるでしょう。
- 評定衆(ひょうじょうしゅう)と引付衆(ひきつけしゅう) ⚖️
- 評定衆と引付衆は、それぞれ将軍や管領の相談役として、重要な政治判断や裁判に関する審議を行いました。特に引付衆は、土地の所有権や借金の返済など、武士たちの間で起こる揉め事を解決する裁判所の役割を担っていました。公正な判断が求められる、とても重要な役職でしたね。
国を治める仕組み:守護と守護大名 🗾
室町幕府は、将軍が京都にいるだけでは、広い日本全体を直接治めることはできませんでした。そこで登場するのが、「守護(しゅご)」と呼ばれる役職です。
- 守護とは?
- 守護は、鎌倉時代から存在した役職で、幕府が任命して各地方に派遣する「地方長官」のようなものです。元々は、その国の治安維持や、「御家人」(ごけにん)たちのまとめ役として置かれました。
- 守護大名への成長!
- 室町時代に入ると、この守護の力がどんどん強くなっていきます。彼らは、自分の担当する国(地域)で、軍事だけでなく、税金を集めたり、裁判を行ったりする権利も持つようになりました。まるでその国のお殿様のような存在になっていったんです。こうして、大きな力を持った守護は、「守護大名(しゅごだいみょう)」と呼ばれるようになりました。
- 守護大名は、自分たちの支配する国に「守護所(しゅごしょ)」と呼ばれる役所を置き、家臣たちを使ってその国を治めていきました。有名な守護大名には、山名氏、「大内氏」(おおうちし)、細川氏などがいます。彼らは、時には将軍を支え、時には将軍と対立することもあり、室町時代の歴史を大きく動かしていく存在となっていきます。
- 室町時代に入ると、この守護の力がどんどん強くなっていきます。彼らは、自分の担当する国(地域)で、軍事だけでなく、税金を集めたり、裁判を行ったりする権利も持つようになりました。まるでその国のお殿様のような存在になっていったんです。こうして、大きな力を持った守護は、「守護大名(しゅごだいみょう)」と呼ばれるようになりました。
諸説あり!室町幕府の権力は強かったの?弱かったの? 🤔
室町幕府の権力がどれくらい強かったのか、あるいは弱かったのかについては、歴史家の間でも色々な考え方があります。
- 「将軍権力が弱かった」という説
- この説を支持する人は、室町幕府は鎌倉幕府と比べて、将軍が全国の武士を直接的に支配する力が弱かったと主張します。
その理由として、先ほど説明した「守護大名」の存在が挙げられます。守護大名たちは、自分の領地では将軍の命令がなくても自由に政治を行うことができたため、将軍が全国に直接命令を下すことが難しかったという見方です。
また、「応仁の乱」(おうにんのらん)のように、幕府の力では有力な守護大名同士の争いを止められず、全国的な大混乱に発展したことも、将軍の力の限界を示すものとされます。
- この説を支持する人は、室町幕府は鎌倉幕府と比べて、将軍が全国の武士を直接的に支配する力が弱かったと主張します。
- 「将軍権力はそこそこ強かった」という説
- 一方で、この説を支持する人は、室町幕府、特に初期や中期においては、将軍の権力は決して弱くはなかったと考えます。
例えば、三代将軍「足利義満」(あしかが よしみつ)は、天皇に代わって「日本国王」と呼ばれたり、中国の明(みん)との貿易(勘合貿易:かんごうぼうえき)を独占したりするなど、非常に強い権力を持っていました。
また、有力な守護大名を将軍が直接任命したり、解任したりすることもできたことから、将軍には守護大名を統制する力があったという見方です。さらに、将軍が各地の守護大名に命令を出して、軍事行動を行わせることもできました。
この説では、むしろ室町幕府は、将軍と守護大名が互いに協力し合いながら、日本の政治を運営していく「二元的な支配体制」だったと捉えることができます。将軍は中央のリーダーとして、守護大名は地方のリーダーとして、それぞれの役割を分担していた、と考えるんですね。
- 一方で、この説を支持する人は、室町幕府、特に初期や中期においては、将軍の権力は決して弱くはなかったと考えます。
どちらの説が正しいか、一概に結論を出すのは難しいですが、どちらの意見も納得できる部分がありますよね。歴史を考えるときは、一つの見方だけでなく、色々な角度から物事を見るのが大切だということを教えてくれる良い例ですね!
室町幕府の財政はどうだったの? 💰
幕府が政治を動かすには、当然ながらお金が必要ですよね。室町幕府は、一体どうやってお金を集めていたのでしょうか?
- 土地からの収入
- 室町幕府も、他の時代の政府と同じように、自分が直接支配する土地(直轄領:ちょっかつりょう)からの年貢(ねんぐ)が主な収入源でした。農民たちが作った米などを税金として納めていたんです。
- 関銭(せきせん)と津料(しんりょう)
- 室町幕府は、交通の要所である関所(せきしょ)で通行料として「関銭」を徴収したり、港で船の利用料として「津料」を徴収したりしていました。これは、現代の高速道路の料金や空港の利用料のようなものですね。人や物の移動が増えるほど、幕府の収入も増えることになります。
- 土倉(どそう)と酒屋(さかや)への課税
- 室町時代には、お金を貸し付ける金融業を行う「土倉」や、お酒を造って売る「酒屋」が栄えました。幕府は、こうした儲かる商売をしている業者から税金を取ることで、財政を潤わせました。これは、現代の法人税や消費税のようなものでしょうか。
- 勘合貿易の利益
- 三代将軍足利義満の時代に始まった、中国の明との「勘合貿易」(かんごうぼうえき)は、幕府に莫大な利益をもたらしました。
これは、明から「勘合符(かんごうふ)」という許可証をもらって行う正式な貿易で、日本の刀剣や硫黄などを輸出し、中国の絹織物や陶磁器などを輸入していました。この貿易を幕府が独占していたため、将軍の財力は非常に豊かになったと言われています。
- 三代将軍足利義満の時代に始まった、中国の明との「勘合貿易」(かんごうぼうえき)は、幕府に莫大な利益をもたらしました。
これらの収入源によって、室町幕府は将軍の豪華な暮らしや、文化の発展、そしてもちろん政治や軍事を運営するための費用をまかなっていたんですね。
室町文化の発展と幕府の役割 🎨
室町時代は、武士の文化と「公家」(くげ)の文化、そして「禅宗」(ぜんしゅう)の影響が混じり合って、非常にユニークで美しい「室町文化」(むろまちぶんか)が花開いた時代でもありました。幕府は、この文化の発展に大きな役割を果たしました。
- 将軍の文化事業
- 特に三代将軍「足利義満」(あしかが よしみつ)や八代将軍「足利義政」(あしかが よしまさ)は、自ら積極的に文化活動を支援しました。義満が建てた「金閣」(きんかく)や、義政が建てた「銀閣」(ぎんかく)は、まさに室町文化を象徴する建物ですよね。
彼らは、「連歌」(れんが)や「茶の湯」(ちゃのゆ)、「能楽」(のうがく)といった芸能や芸術を保護し、多くの文化人を招いて交流を深めました。
- 特に三代将軍「足利義満」(あしかが よしみつ)や八代将軍「足利義政」(あしかが よしまさ)は、自ら積極的に文化活動を支援しました。義満が建てた「金閣」(きんかく)や、義政が建てた「銀閣」(ぎんかく)は、まさに室町文化を象徴する建物ですよね。
- 禅宗の影響
- 室町幕府は、禅宗を深く信仰し、禅寺を保護しました。禅宗は、武士の精神と結びつき、「水墨画」(すいぼくが)や「枯山水」(かれさんすい)の庭園など、日本の美意識に大きな影響を与えました。
- 地方への文化伝播
- 幕府が京都で文化活動を盛んに行うことで、その文化は全国の守護大名たちにも広がっていきました。守護大名たちも、自分たちの領地で文化人を招いたり、寺院を建立したりするなど、文化の保護・育成に努めました。
このように、室町幕府は単なる政治機関としてだけでなく、日本の文化を育む「文化センター」のような役割も果たしていたんですよ。
室町幕府の終焉、そして戦国時代へ… 💥
長い歴史を持つ室町幕府も、永遠に続いたわけではありません。
- 応仁の乱の勃発
- 1467年(応仁元年)に始まった「応仁の乱」(おうにんのらん)は、室町幕府の衰退を決定づける大きな出来事でした。将軍家の跡継ぎ問題や、有力な守護大名同士の権力争いが複雑に絡み合い、京都を舞台にした大規模な内乱へと発展しました。この戦いは10年以上も続き、京都の街は焼け野原となり、幕府の権威は地に落ちていきました。
- 下剋上(げこくじょう)の時代へ
- 応仁の乱をきっかけに、全国各地で守護大名の力が弱まり、家臣や「国人」(こくじん)と呼ばれる地方の有力者たちが、それまでの主君に取って代わる「下剋上」(げこくじょう)の風潮が強まっていきました。これにより、幕府の統制が及ばない「戦国時代」へと突入していくことになります。
- 織田信長(おだのぶなが)による滅亡
- そして、1573年(元亀4年/天正元年)、織田信長が最後の将軍「足利義昭」(あしかが よしあき)を京都から追放したことで、室町幕府はその歴史に幕を下ろしました。約240年続いた室町幕府の時代は、こうして終わりを告げ、日本は統一を目指す新たな時代へと進んでいくことになるのです。
室町幕府の仕組み まとめ
室町幕府は、足利将軍を中心に、管領、侍所、政所などの組織が連携して政治を動かしていました。地方では守護大名が大きな力を持っていましたが、彼らもまた幕府の権威の下にありました。
その権力の強弱は諸説ありますが、将軍と守護大名が協力し合うことで、国を統治していたと言えるでしょう。また、独自の経済基盤を持ち、豊かな室町文化を育んだことも、この時代の大きな特徴でした。
しかし、やがて有力な守護大名の台頭や、応仁の乱のような内乱を経て、幕府の力は衰え、ついに織田信長によって滅ぼされることになります。室町幕府の歴史は、日本の政治体制がどのように変化していったのか、そして武士たちがどのように国を動かしてきたのかを学ぶ上で、とても重要な時代なんですよ!
今回の授業はいかがしたか?少しは室町幕府の仕組みについて理解が深まりましたか?
主要人物紹介 🧑🤝🧑
| 名前 | 略歴 | 役割 |
| 足利尊氏 | 鎌倉幕府を倒した後、室町幕府を開いた初代将軍。 | 室町幕府の創始者。武士による新しい政府を樹立。 |
| 足利義満 | 室町幕府の三代将軍。北山文化を代表する金閣を建立。日明貿易を推進。 | 最盛期の将軍。幕府の権威と経済力を確立。 |
| 足利義政 | 室町幕府の八代将軍。東山文化を代表する銀閣を建立。応仁の乱を招いた。 | 室町文化の発展に貢献。幕府衰退期の将軍。 |
| 織田信長 | 戦国時代の武将。室町幕府を滅ぼし、天下統一を推し進めた。 | 室町幕府を滅ぼした人物。 |
キーワード一覧 🔑
| キーワード | 説明 | 重要度 |
| 室町幕府 | 足利尊氏によって京都の室町に開かれた武士の政府。1336年~1573年。 | ★★★ |
| 将軍 | 室町幕府の最高権力者。征夷大将軍の称号を持つ。 | ★★★ |
| 管領 | 将軍を補佐し、幕府の政務を総括する最高職。細川・斯波・畠山の三家が交代で務めた。 | ★★ |
| 三管領 | 管領を務めた細川氏、斯波氏、畠山氏の三家の総称。 | ★ |
| 侍所 | 幕府の軍事・警察を担う機関。治安維持や犯罪者の逮捕などを行った。 | ★★ |
| 四職 | 侍所の所司を務めた赤松氏、一色氏、山名氏、京極氏の四家の総称。 | ★ |
| 政所 | 幕府の財政や訴訟事務を担当する機関。 | ★★ |
| 守護 | 各地方に派遣され、治安維持や御家人の統制を行った幕府の役職。 | ★★★ |
| 守護大名 | 室町時代に、広い領地と強い軍事力を持つようになった有力な守護。 | ★★★ |
| 応仁の乱 | 1467年から1477年にかけて京都を中心に起こった大規模な内乱。室町幕府衰退のきっかけとなった。 | ★★★ |
| 下剋上 | 弱い者が強い者に打ち勝ち、身分が下の者が上の者に取って代わること。戦国時代の特徴。 | ★★ |
| 関銭・津料 | 関所や港で徴収された通行料・利用料。幕府の重要な財源。 | ★ |
| 土倉・酒屋への課税 | 金融業や酒造業を営む業者から徴収された税金。 | ★ |
| 勘合貿易 | 室町幕府と中国の明との間で行われた正式な貿易。将軍の独占事業で、幕府の財源となった。 | ★★ |
| 室町文化 | 室町時代に花開いた文化。武士、公家、禅宗の影響が混じり合う。金閣・銀閣が代表的。 | ★★ |
略年表 🗓️
| 年代 | 出来事 |
| 1336年 | 足利尊氏が室町幕府を成立させる。(南北朝時代が始まる) |
| 1392年 | 足利義満が南北朝を統一する。 |
| 1397年 | 足利義満が金閣を建立する。 |
| 1467年 | 応仁の乱が始まる。 |
| 1477年 | 応仁の乱が終結する。 |
| 1489年 | 足利義政が銀閣を建立する。 |
| 1573年 | 織田信長が足利義昭を追放し、室町幕府が滅亡する。 |
アイコン例
- 👑:王冠、トップ、最高権力者
- 🏢:建物、組織、役所
- 📋:書類、記録、事務
- ⚔️:刀、武士、軍事
- 💰:お金、財政、経済
- ⚖️:天秤、裁判、公平
- 🗾:日本地図、国、地方
- 🤔:考える人、疑問、諸説
- 🎨:絵の具、芸術、文化
- 💥:爆発、争い、崩壊
理解度チェック 📝
- 室町幕府を開いた人物は誰ですか?
- 将軍を補佐し、幕府の政治を総括する最高職の名称は何ですか?
- 室町時代に、各地で大きな力を持つようになった地方の武士の呼び名は何ですか?
- 室町幕府の衰退を決定づけた、京都を舞台に起こった大規模な内乱の名前は何ですか?
- 室町幕府の財源の一つで、中国の明との間で行われた正式な貿易の名前は何ですか?
解答と解説
- 足利尊氏
- 解説:足利尊氏が、鎌倉幕府を倒した後に、京都に新しい武士の政府である室町幕府を開きました。
- 管領(かんれい)
- 解説:管領は、将軍の次に偉い役職で、将軍を補佐して幕府の政治を総括する役割を担っていました。細川氏、斯波氏、畠山氏の三家が交代で務めたので「三管領」と呼ばれます。
- 守護大名(しゅごだいみょう)
- 解説:室町時代になると、各地に派遣された守護が、自分の領地で大きな力を持つようになり、守護大名と呼ばれるようになりました。彼らは、時には幕府に協力し、時には対立する存在でした。
- 応仁の乱(おうにんのらん)
- 解説:1467年に始まった応仁の乱は、将軍家の跡継ぎ問題や有力守護大名同士の対立が原因で起こった、約10年間続く大規模な内乱です。この乱によって幕府の権威は大きく失われ、戦国時代へと突入するきっかけとなりました。
- 勘合貿易(かんごうぼうえき)
- 解説:三代将軍足利義満の時代に始まった、中国の明との貿易です。「勘合符」という許可証を使って行われ、幕府に大きな利益をもたらしました。
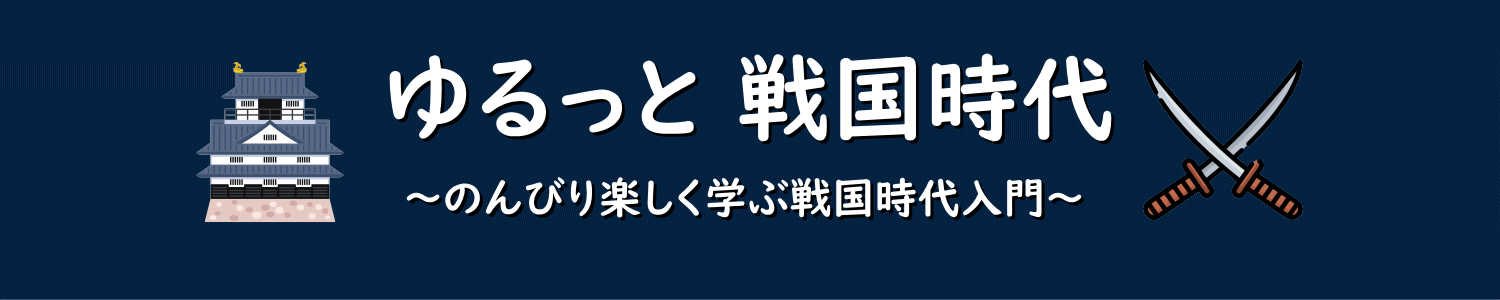
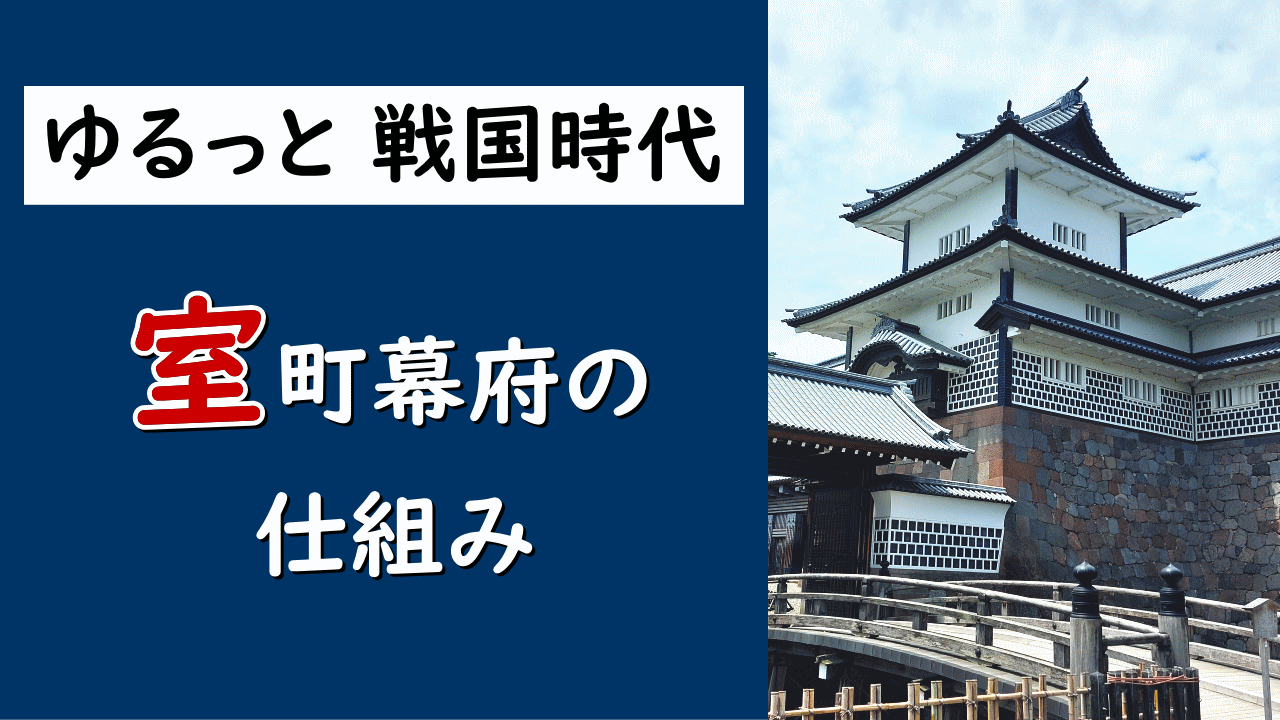
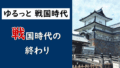
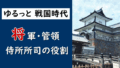
コメント