みなさん、こんにちは!
今回は皆さんと一緒に、たくさんの英雄たちが登場し、日本の歴史の中でも特に人気の高い「戦国時代」が、一体いつから始まったのか、その謎を探る旅に出たいと思います。
一口に「始まり」と言っても、実は「ここから!」と一本の線を引くのがとても難しい時代なんです。いくつかの説があるので、それぞれの説をじっくりと見ていきながら、なぜそのように考えられているのかを、一緒に解き明かしていきましょう!
❓そもそも戦国時代ってどんな時代?
皆さんが「戦国時代」と聞いて思い浮かべるのは、どんなイメージでしょうか?織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった有名な武将たちが、天下統一を目指して戦う…そんな「群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)」や「下剋上(げこくじょう)」のイメージが強いかもしれませんね。
まさにその通りで、戦国時代とは、これまで日本をまとめていた室町幕府(むろまちばくふ)の力が弱まり、全国の武士たちが実力で領地を奪い合い、のし上がっていく、まさに「力こそ正義」の時代でした。身分が下の者が、実力で上の者を倒してその地位を奪う「下剋上」が当たり前のように起こったのです。
この時代は、一般的に室町時代の後半にあたる15世紀の半ば頃から、豊臣秀吉が天下を統一する16世紀の終わり頃まで、約150年間続いたとされています。
では、この長い戦乱の時代の「始まりのゴング」は、一体どの出来事によって鳴らされたのでしょうか。実は、これには主に4つの有力な説があるんですよ。一緒に見ていきましょう!
説1 🔥 最も有名!「応仁の乱」(1467年) 始まり説
まず、最も多くの教科書に載っていて、一般的に「戦国時代の始まり」と言われているのが、1467年(応仁元年)に京都で始まった「応仁の乱」(おうにんのらん)です。なぜ、この戦が時代の大きな転換点になったのでしょうか。
応仁の乱が起こった背景
応仁の乱が起こった頃、室町幕府のトップである将軍の力は、すっかり弱くなっていました。8代将軍・「足利義政」(あしかが よしまさ)は、政治よりも文化的な活動に熱心な人物で、政治の細かいことは有力な家臣である「守護大名(しゅごだいみょう)」たちに任せきりになっていました。
この守護大名とは、幕府から任命されて、各地方(国)の警察権や軍事権を任されていた、いわばエリート武士のことです。彼らは京都に自分の屋敷を持ち、幕府の政治に参加していましたが、その中でも特に力を持っていたのが、「細川勝元」(ほそかわ かつもと)と「山名宗全」(やまな そうぜん)という二人の大物でした。
この二人は、もともと親戚関係にあったりもしたのですが、幕府内での権力争いから、次第に対立を深めていきます。そんな一触即発の状況で、火に油を注ぐ出来事が2つも起こってしまったのです。
- 将軍家の後継者問題
将軍・足利義政には、なかなか跡継ぎの男の子が生まれませんでした。そこで義政は、弟の「足利義視」(あしかが よしみ)を次の将軍にしようと決めます。しかし、その直後になんと、正室の「日野富子」(ひの とみこ)との間に男の子、「足利義尚」(あしかが よしひさ)が誕生してしまったのです!
「自分の子を将軍にしたい!」と願う日野富子と、一度は将軍になることを約束された義視。この対立に、山名宗全が日野富子と義尚を、細川勝元が義視を、それぞれ応援する形で介入し、対立はさらに深まります。 - 有力大名の家督争い
ちょうど同じ頃、有力な守護大名であった「畠山氏」(はたけやまし)と「斯波氏」(しばし)の家の中でも、誰が家のリーダー(家督)になるかを巡って争いが起きていました。この家の争いにも、細川勝元と山名宗全がそれぞれ別の候補者を応援する形で介入します。
つまり、将軍家の後継者問題と、有力大名の家督争いという2つの火種が、細川勝元と山名宗全という二大勢力の対立と結びついてしまったのですね。こうして、日本全国の武士を巻き込む大戦争、「応仁の乱」の準備が整ってしまったのです。
応仁の乱の経過と影響
1467年(応仁元年)、ついに両軍が京都で激突します。細川方が「東軍」、山名方が「西軍」と呼ばれ、京都の市街地は焼け野原となりました。この戦いは、なんと11年もの長きにわたって続きます。
戦いが長引くにつれて、初めの目的だった後継者争いなどはどうでもよくなってしまいました。戦いの途中で、主要人物であった山名宗全も細川勝元も病死してしまいます。それでも戦いは終わらず、京都だけでなく、それぞれの守護大名が領地としている地方にも戦火が広がっていきました。
この長くて大きな戦乱が、日本社会に与えた影響は計り知れません。
- 👑 将軍・幕府の権威が地に落ちた
京都を戦場にされ、それを止める力もなかった将軍や幕府の権威は、完全に失墜しました。「もう幕府に国を治める力はない」ということが、誰の目にも明らかになってしまったのです。 - ⚔️ 守護大名の力が弱まった
多くの守護大名は、京都での長い戦いのために、自分たちの領地を空けていました。その隙に、領地を守っていた家来である「守護代(しゅごだい)」や、その土地の有力者である「国人(こくじん)」たちが力をつけていきました。そして、「領地は、京都にいる殿様のものではなく、実際に治めている俺たちのものだ!」と考えるようになります。これが、まさしく「下剋上」の始まりでした。 - 🌾 古い土地制度が壊れた
戦乱によって、貴族や寺社が持っていた「荘園」(しょうえん)と呼ばれる私有地は、近くの武士たちに奪われていきました。これまで国を支えてきた土地の仕組みが、根本から崩れていったのです。
このように、応仁の乱は、それまでの日本の秩序を完全に破壊し、誰もが実力でのし上がれる新しい時代、つまり「戦国時代」への扉を開いた出来事だと考えられているのです。だからこそ、多くの人がこの乱を「戦国時代の始まり」と見なしているのですね。
説2 ⚔️ 下剋上の決定打!「明応の政変」(1493年) 始まり説
次にご紹介するのは、「いや、応仁の乱はまだ序章に過ぎない。本当の戦国時代の始まりは、この出来事からだ!」と考える専門家も多い、「明応の政変」(めいおうのせいへん)説です。
これは、1493年(明応2年)に起こった、ある意味で応仁の乱よりも衝撃的なクーデター事件でした。
明応の政変とは?
応仁の乱で東軍を率いた細川勝元の子供、「細川政元」(ほそかわ まさもと)は、父の権力を引き継ぎ、幕府の政治を牛耳っていました。
この頃の将軍は、応仁の乱のきっかけの一人でもあった足利義視の子供、「足利義材」(あしかが よしき、後の義稙(よしたね))でした。義材は、将軍としての権力を取り戻そうと、自ら軍を率いて河内国(現在の大阪府東部)の畠山氏を討伐に出かけます。
しかし、政元はこの将軍の動きを快く思っていませんでした。「将軍がこれ以上力をつけては、自分の思い通りに政治ができなくなる」と考えたのです。
そこで政元は、将軍が京都を留守にしている隙を狙って、クーデターを起こします。なんと、将軍・義材をクビにして捕らえ、代わりに自分が操りやすい別の人物(足利義澄)を新しい将軍として立ててしまったのです!
なぜこれが重要なのか?
考えてみてください。これまで、将軍というのは幕府のトップであり、誰もが敬うべき存在でした。その将軍を、家臣であるはずの細川政元が、自分の都合で勝手にクビにして、新しい将軍を立ててしまった。これは前代未聞の出来事です。
応仁の乱で幕府の権威が「弱まった」のだとすれば、この明応の政変は、幕府の権威が「完全に無くなった」ことを象徴する出来事だと言えます。
「もはや将軍は、力のある者の『お飾り』でしかない」という事実が、はっきりと示されたのです。これは、まさに下剋上が当たり前の世の中になったことを意味します。そのため、この「明応の政変」こそが、実質的な戦国時代のスタート地点だと考える説も、非常に有力なんですよ!
説3 関東から始まった!「享徳の乱」(1455年) 始まり説
ここまでは京都で起きた出来事を見てきましたが、少し視点を変えて、関東地方に注目してみましょう。「戦国の動乱は、実は京都より早く、関東で始まっていたんだ!」という説が、この「享徳の乱」(きょうとくのらん)始まり説です。
享徳の乱とは?
この乱は、応仁の乱よりも12年も早い1455年(康生元年)に始まりました。 当時、関東地方は、鎌倉に拠点を置く「鎌倉公方(かまくらくぼう)」という役職の足利氏が治めていました。これは、京都の室町幕府の出先機関のようなものです。そして、その鎌倉公方を補佐する役職として「関東管領(かんとうかんれい)」の「上杉氏」(うえすぎし)がいました。
しかし、代を重ねるうちに鎌倉公方は独立志向を強め、京都の幕府や関東管領の上杉氏と対立するようになります。そして、鎌倉公方・「足利成氏」(あしかが しげうじ)が、対立していた関東管領・「上杉憲忠」(うえすぎ のりただ)を暗殺したことから、関東全域を巻き込む大規模な戦争が始まってしまいました。これが享徳の乱です。
この戦いは、なんと約30年も続きました。その結果、関東は、古河(こが)を本拠地とする足利成氏の「古河公方」(こがくぼう)と、幕府が新たに派遣した「堀越公方」(ほりごえくぼう)および関東管領上杉氏の勢力に分裂し、泥沼の戦いを続けることになります。
なぜこれが始まりの説になるのか?
応仁の乱が始まるよりもずっと前から、関東では幕府のコントロールが効かない大規模な戦乱が続いていました。守護大名同士が争い、領地を奪い合うという、まさに「戦国時代」そのもののような状況が、すでに生まれていたのです。
この説は、「戦国時代とは、幕府の統制が効かなくなった状態」と定義するならば、その始まりは京都の応仁の乱ではなく、関東の享徳の乱に見るべきだ、という考え方に基づいています。日本の中心である京都だけでなく、地方で起こっていたことに目を向ける、とても興味深い説ですよね!
説4 🏯 新しい支配者の登場!「北条早雲の伊豆討ち入り」(1493年頃) 始まり説
最後にご紹介するのは、これまでの「戦乱」ではなく、「人物」に注目した説です。戦国時代を象徴する存在、それは実力で領地を支配する「戦国大名」です。この戦国大名のパイオニアとされる「北条早雲」(ほうじょう そううん/または「伊勢盛時」(いせ もりとき))の登場を、戦国時代の始まりと見る説です。
北条早雲とは?
北条早雲は、少し前までは「素性の知れない素浪人から、実力一つで大名に成り上がった下剋上の天才」というイメージで語られてきました。しかし最近の研究では、彼は室町幕府の役人を務める、ちゃんとした家柄の出身(伊勢盛時というのが本名)であったことが分かっています。
彼は、親戚関係にあった駿河国(現在の静岡県中部)の「今川氏」(いまがわし)のお家騒動を解決した功績で、領地をもらいます。そして、そこを足掛かりに、1493年(明応2年)頃、隣の伊豆国(現在の静岡県伊豆半島)に攻め込み、実力でこれを乗っ取ってしまいました。
この時、早雲が攻め取った相手は、先ほどの享徳の乱で登場した「堀越公方」の「足利茶々丸」(あしかが ちゃちゃまる)でした。幕府が関東を治めるために派遣した、由緒正しい足利一門を、幕府の役人に過ぎなかった早雲が滅ぼしてしまったのです。
なぜこれが重要なのか?
早雲の行動は、これまでの武士の常識を打ち破るものでした。
- 彼は、幕府から任命された「守護」という権威に頼りませんでした。ただ純粋に「軍事力」で領地を奪い、自分のものにしたのです。
- そして、奪った領地で独自の法律(検地や税制などを定めたもので「分国法」(ぶんこくほう)って言います)を定め、民衆の心をつかみながら、直接的で強力な支配体制を築き上げていきました。
このような、幕府の権威に頼らず、自らの実力で領国を切り取り、独自のやり方で支配する武士こそが「戦国大名」(せんごくだいみょう)です。
北条早雲は、その「戦国大名」という新しいタイプの支配者の、いわば第一号でした。そのため、古い秩序(守護大名)から新しい秩序(戦国大名)への転換点として、早雲の伊豆討ち入りを戦国時代の始まりと考えるのです。
奇しくも、この出来事は京都の「明応の政変」とほぼ同じ時期に起こっています。中央でも地方でも、新しい時代への大きなうねりが起きていた証拠かもしれませんね。
📖 主要人物の紹介
ここで、今回の話に登場した主要な人物たちを、表で整理しておきましょう。
| 名前 | 略歴 | 役割 |
| 足利 義政 (あしかが よしまさ) | 室町幕府 第8代将軍。 | 政治にはあまり関心がなく、銀閣の建立など文化活動に力を注いだ。彼の後継者問題が応仁の乱の引き金の一つとなった。 |
| 細川 勝元 (ほそかわ かつもと) | 室町幕府の管領(将軍の補佐役)。有力守護大名。 | 応仁の乱では東軍の総大将。将軍家の後継者問題や畠山・斯波氏の家督争いに介入し、山名宗全と対立した。 |
| 山名 宗全 (やまな そうぜん) | 有力守護大名。「赤入道」の異名を持つ。 | 応仁の乱では西軍の総大将。細川勝元と幕府の主導権を巡って争い、日本全土を巻き込む大乱を引き起こした。 |
| 日野 富子 (ひの とみこ) | 足利義政の正室。 | 息子・義尚を将軍に擁立するため、山名宗全と手を結んだ。悪女として語られることもあるが、政治力に長けた女性だった。 |
| 細川 政元 (ほそかわ まさもと) | 細川勝元の子。幕府の管領。 | 1493年にクーデター(明応の政変)を起こし、将軍・足利義材を追放。幕府の権威を完全に失墜させ、下剋上を象徴する人物。 |
| 北条 早雲 (ほうじょう そううん) | 戦国大名の先駆けとされる武将。本名は伊勢盛時。 | 幕府の役人出身。実力で伊豆国を奪い(伊豆討ち入り)、新しい形の領国支配を始めた。後に関東に巨大な勢力を築く後北条氏の祖。 |
✨ 重要キーワードの解説
今回の話を理解する上で、特に重要な言葉をまとめておきますね。
| キーワード | 説明 | 重要度 |
| 応仁の乱 | 1467年から11年間続いた全国規模の内乱。室町幕府の権威を失墜させ、戦国時代の幕開けとされる最も有力な説。 | ★★★ |
| 下剋上 | 身分が下の者が、実力で上の者を倒して、その地位や権力を奪い取ること。戦国時代を象徴する言葉。 | ★★★ |
| 守護大名 | 室町幕府によって、地方の軍事・警察権などを任されていた有力な武士。鎌倉時代の「守護」が、領地を私物化して大名化したもの。 | ★★☆ |
| 明応の政変 | 1493年、細川政元が将軍を追放したクーデター。将軍が無力であることを天下に示し、下剋上を決定づけた事件。 | ★★☆ |
| 戦国大名 | 幕府の権威に頼らず、自らの実力で領国を支配した武士たち。独自の法律を作り、領国経営を行った。北条早雲がその先駆けとされる。 | ★★★ |
| 守護代・国人 | 守護代は、守護大名の家来で、領地の管理を代行していた者。国人は、その土地に根差した地元の有力武士。彼らが力をつけ、下剋上を行う主体となった。 | ★☆☆ |
📜 略年表
今回の出来事を、時間の流れで確認してみましょう。
- 1455年 – 享徳の乱が始まる(関東での大乱)。
- 1467年 – 応仁の乱が始まる(京都での大乱)。
- 1477年 – 応仁の乱が終わる。
- 1485年 – 山城国一揆が起こる(武士を追い出し、国人が8年間自治を行う)。
- 1493年頃 – 北条早雲が伊豆に討ち入る(戦国大名の登場)。
- 1493年 – 明応の政変が起こる(細川政元が将軍を追放)。
まとめ
さて、ここまで戦国時代の始まりに関する4つの説を見てきましたが、いかがでしたでしょうか?
- 🔥応仁の乱(1467年)説:古い秩序の崩壊の始まり
- ⚔️明応の政変(1493年)説:下剋上の決定的な象徴
- 🪖享徳の乱(1455年)説:関東で先行した戦乱
- 🏯北条早雲の伊豆討ち入り(1493年頃)説:新しい支配者「戦国大名」の登場
このように、何をもって「始まり」と考えるかで、その時期は変わってきます。
「政治的な混乱」に注目するのか、「社会の仕組みの変化」に注目するのか、あるいは「新しいタイプのリーダーの登場」に注目するのか…。歴史の見方には、色々な角度があるということが、お分かりいただけたかと思います。
ただ、一般的には、やはり「応仁の乱」が戦国時代という長い動乱期の開幕を告げる、大きな狼煙(のろし)であった、と考えるのが分かりやすいでしょう。この乱によって、それまで人々が当たり前だと思っていた「幕府」という巨大な権威が崩れ去り、「力さえあれば誰でも天下を狙える」という新しい価値観が生まれたのです。
この大混乱の中から、やがて織田信長や豊臣秀吉のような、新しい時代を作る英雄たちが登場してくることになります。戦国時代の始まりを知ることは、彼らがなぜ登場する必要があったのかを理解するための、とても大切な第一歩なんですよ!
これから皆さんが歴史を学んでいく上で、今日の話が少しでも役立てば嬉しいです。
アイコン例の説明
- ❓: 疑問や問いかけを表す際に使用しました。
- 🔥: 戦乱や大きな出来事の象徴として使用しました。
- ⚔️: 戦いや下剋上といった、武力による行動を表す際に使用しました。
- 🏯: 城や大名、領国支配の象徴として使用しました。
- 👑: 将軍や天皇など、最高の権威を表す際に使用しました。
- 🌾: 土地や民衆の生活に関連する事柄を表す際に使用しました。
- 📖: 人物紹介など、解説的な部分で使用しました。
- ✨: キーワードなど、特に注目してほしい用語の際に使用しました。
- 📜: 年表など、歴史の流れを示す際に使用しました。
- 🪖: 関東の乱など、特定の地域の武士や戦いを表す際に使用しました。
理解度チェック
さあ、今回の学習内容がどれだけ身についたか、簡単なクイズで試してみましょう!
【問題】
- 一般的に「戦国時代の始まり」と言われる、1467年に京都で始まった11年続く大乱の名前は何でしょうか?
- 応仁の乱で、東軍の総大将だった人物と、西軍の総大将だった人物はそれぞれ誰でしょう?
- 家臣である細川政元が将軍を追放した、下剋上を象徴する1493年のクーデター事件を何と呼びますか?
- 京都での応仁の乱より早く、関東地方で始まっていた大規模な戦乱は何でしょうか?
- 「戦国大名のパイオニア」とされ、実力で伊豆国を支配下に置いた武将は誰でしょう?(本名ではなく、有名な方の名前で答えてください)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【解答と解説】
- 答え: 応仁の乱(おうにんのらん)
- 解説: 室町幕府の権威を決定的に失墜させ、全国的な戦乱の時代を招いたため、戦国時代の始まりとする説が最も有力です。
- 答え: 東軍:細川勝元(ほそかわかつもと)、西軍:山名宗全(やまなそうぜん)
- 解説: この二人の有力守護大名の対立が、将軍家の後継者問題などと結びつき、応仁の乱へと発展しました。
- 答え: 明応の政変(めいおうのせいへん)
- 解説: この事件により、将軍は力のある者の傀儡(かいらい、あやつり人形)に過ぎないことが明らかになりました。これも戦国時代の始まりとする有力な説です。
- 答え: 享徳の乱(きょうとくのらん)
- 解説: 応仁の乱より12年も早い1455年に始まっています。関東では一足先に戦国的な状況が生まれていたことを示す出来事です。
- 答え: 北条早雲(ほうじょうそううん)
- 解説: 彼の伊豆討ち入りは、守護大名とは違う、実力でのし上がる「戦国大名」の時代の幕開けと見る説の根拠となっています。
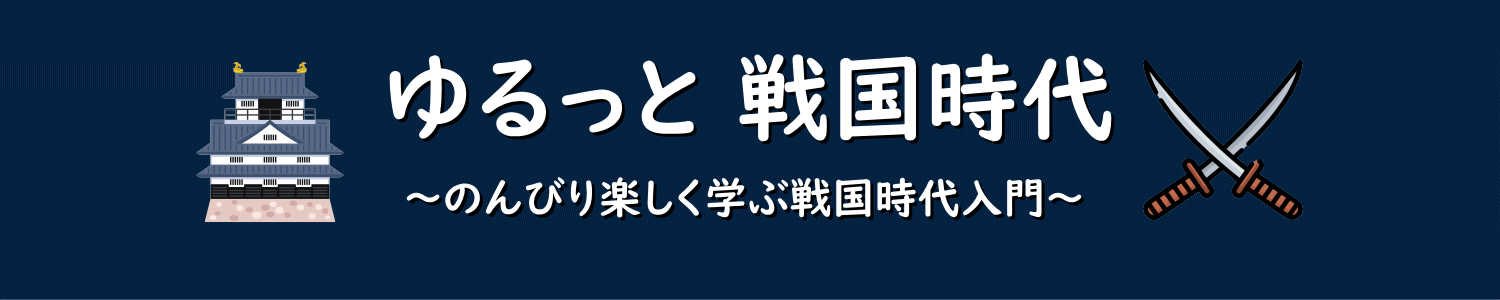
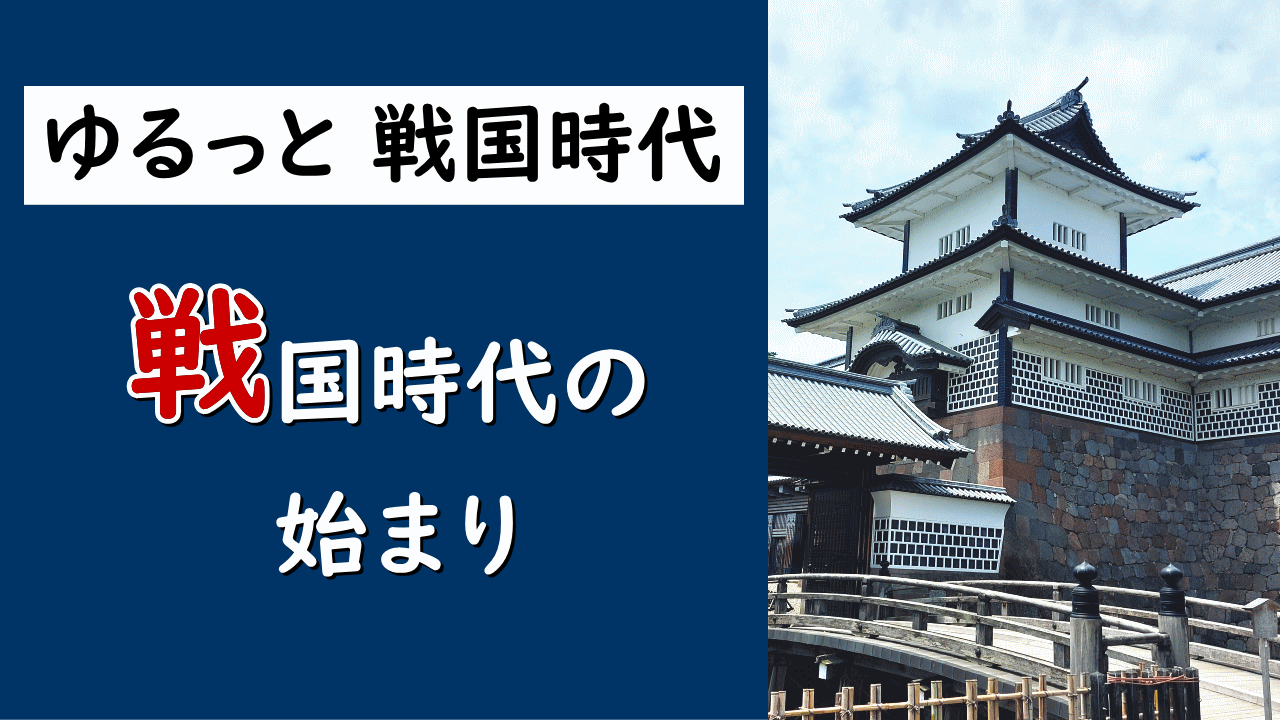
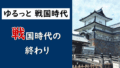
コメント